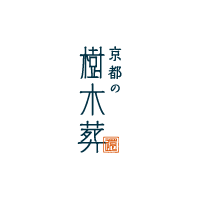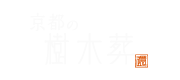京都の樹木葬墓地におけるアンケート調査報告
2025/11/22下記のアンケート調査結果は、カン綜合計画がプロデュースした樹木葬の契約者へ行ったアンケート結果について、筑波大学大学院 内田安紀さんが2018年に考察しまとめたものです。
まえがき
京都の樹木葬墓地におけるアンケート調査報告書
樹木葬という形態が日本に登場してから18年を数えるが、その間、これまでいくつかの樹木葬墓地で調査が行われ、樹木葬墓地の申込者には「脱継承」と「自然志向」の傾向があると言われてきた。しかし一方で、「樹木葬」という形態自体も、様々な運営母体によって多様な解釈がなされ、独自の発展を遂げている。
今回調査対象となった京都市内四つの塔頭寺院の樹木葬墓地は、近年になって見られるようになった「街中の樹木葬」とも呼べる新しいタイプの樹木葬墓地であり、かつ、京都という観光名所に立地する大本山塔頭寺院というブランド性を持った独特の墓地である。特に立地に関していえば、これまで主流であった樹木葬は、地方の寺院によって地元の自然環境保全のために設けられる場合、また地方自治体や民間企業によって郊外の大規模霊園の一角に取り入れられる場合が多く、住宅地や商業施設などの日常空間と隣接する墓地はほとんど見られなかった。これらの樹木葬墓地は「里山型(農村型)」「都市型(公園型)」など、その立地による大まかな区分はありつつも、前者においては樹木葬墓地造成のための山林を確保する必要性から、また後者においては多くの墓地需要を受け入れるための広大な面積を有する必要性から、街中に存在することはほとんど不可能であった。しかしながら、今回のように、もともと街中に位置していた寺院の境内を整理する場合は、新たに墓地区画としての認定が必要でないため、地目はそのままに、都市の内部に樹木葬墓地を造成することが可能となる。その意味で、「街中の樹木葬」が出現するためには、もともと都市部に墓地を有していた寺院の存在が不可欠であったと言える。
山の中で行われるイメージの強かった樹木葬だが、それが都市の内部に出現した場合、どのような形をとり、またどのように人々に受容されるのだろうか。今回は、調査地の特徴である「都市性」「京都という観光地」などの要素に着目しながら、「街中の樹木葬」がどのように人々に受容されているのかを知るため、寺院での樹木葬墓地をプロデュースする有限会社カン綜合計画の全面的協力により、二回にわたる墓地申込者へのアンケート調査とヒアリング調査を行った。第一回目のアンケートは郵送にて墓地申込者のいる世帯へ配布し、二回目の追加アンケートは2017年10月に行われた合同供養祭当日に配布し、集計した。ヒアリング調査は前述の合同供養祭にて一人あたり15分~30分程度の時間をかけ、対面式で行った。今回の報告書では、まず研究代表者である筑波大学大学院の内田安紀が、全体アンケートと追加アンケートの結果を、ヒアリング調査で得られた知見を援用しながら紹介する。そしてこの結果について、現代墓制における樹木葬の位置付けという観点から京都女子大学の槇村久子教授が、葬儀の変遷という観点から国立歴史民俗博物館の山田慎也准教授が、それぞれ自身の関心から分析やコメントを加える。
最後に、この調査を行うにあたり、(有)カン綜合計画とその代表である山崎譲二氏に多大なお力添えをいただいたことに感謝申し上げます。また、荘厳院、即宗院、正受院、両足院のご住職、ならびに調査に協力いただいた会員のみなさまにも、ここに記して感謝の意を表します。
1井上治代・千坂嶹峰編 2003 『樹木葬を知る本』 三省堂、 p.182-185。
(2018.4.21 内田安紀)
全体アンケートと追加アンケートの結果報告
1.全体アンケート
調查方法
筑波大学大学院 内田安紀
カン綜合計画がプロデュースする、建仁寺塔頭両足院の「緑雲苑」、大徳寺塔頭正受院の「茈林壇」、東福寺塔頭即宗院の「自然苑」、東福寺塔頭荘厳院の「樹木葬」という、京都市内四つの樹木葬墓地申込者を対象に、郵送にて質問票を配布し、返送してもらう形で回収した。2017年9月1日にカン綜合計画より一斉発送し、回収期間は2017年9月2日~10月20日。総配布数は473票(両足院164 正受院 69、 即宗院 205、 荘厳院 35)、 最終的な回収数は 389 票(両足院 135、正受院 60、 即宗院 166、荘厳院 28)、回収率は 82.24%となった。なお、 契約者のいる家庭一軒につき一票を配布したため、総契約者数と総配布数は同じではない。
まずは回答者の属性を、アンケート票のF1~F9の結果から見ていきたい。
今回のアンケートでは、回答者の性別は男性が183人(47.04%)、女性203人(52.19%)、無回答が3人(0.77%)となっている。アンケート回答時での回答者の年齢は30歳代90歳代にかけて分布しており(図1)、平均年齢は、回答者382人の中でおよそ69.0歳であった。年齢分布は60歳代70歳代が多く、定年退職後、自身の墓や両親の墓を考える年齢の回答者の割合が高いことがわかる。しかし、40歳代50歳代の、比較的若い世代の契約者も1割程度いる。なお、樹木葬墓地購入時の平均年齢は、回答者数365人中の中でおよそ66.60歳であり、回答時よりも若干低くなっている。
次に回答者の既婚・未婚などの別を見てみると、「既婚」243人(62.47%)、「死別」93人(23.91%)、「離別」23人(5.91%)、「未婚」20(5.14%)人、無回答10人(2.57%)であった(図2)。およそ9割の人に結婚の経験があり、回答者の多くが家庭を持っている、あるいは持っていたということがわかる。
そこで、次に子供の有無や性別、人数を見てみると、子供がいる場合にその人数と性別を記入してもらう方式にした設問には、子供の人数については303人(全体の77.89%)からの回答があり、少なくとも回答者のおよそ7割以上に子供がいることがわかった。設問回答者の子供の平均人数は2.01人となった。子供の性別については298人からの回答があり、その中では「男子のみ」が70人(23.49%)、「女子のみ」が111人(37.25%)、「男女両方」が117人で39.26%となった(n=298)。子供がいる回答者の母数を先に見た306人とし、回答しなかった場合を「子供なし」と仮定するならば、「記入なし(子供なし)」が87人(22.37%)、「男子のみ」が70人(17.99%)、「女子のみ」が111人(28.53%)、「男女両方」が117人(30.08%)、「子供はいるが性別無回答」が4人(1.03%)となる(n=389、図3)。ただし、この割合はあくまで正しく全員が「子供がいない場合は無記入」と理解し実行した場合であるので、見落としなどで事実に反して無記入とする場合がある可能性を考慮に入れると、正確な数字ではないことを念頭に置く必要がある。しかし、その場合にも、少なくとも全体のおよそ5割弱の人に、墓を継承しやすい男子がいることがわかる。このように、墓を継承する可能性が高い男子がいる割合と、そうではない場合(女子のみと子供なし)の割合がおおよそ半々であることは、先に複数の樹木葬墓地で行われているアンケート調査と同じ傾向を示している。すなわち、樹木葬を選択する人々は、必ずしも継承者の不在を主要な動機としている訳ではないということである。この動機については後に詳しく見ていく。
次に、回答時における回答者の居住地を見てみると、回答者の居住地は北海道から沖縄まで幅広いが、全体的な傾向としてはやはり、墓地のある京都府やその周辺に住んでいる人の割合が高い。地域別に見てみると、回答者373人中、北海道・東北地方(北海道、青森県、宮城県、福島県)に住んでいる人が5人(1.34%)、関東地方(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、埼玉県、群馬県)が78人(20.91%)中部地方(長野県、静岡県、愛知県、石川県、福井県、三重県、岐阜県)が19人(5.09%)、近畿地方(京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県)が249人(66.75%)、中国地方(広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県)が9人(2.41%)、四国地方(香川県、愛媛県、高知県)7人(1.88%)、九州地方(福岡県、鹿児島県、沖縄県)が6人(1.61%)となった(n=373、図4)。近畿地方の中でも、京都府に在住の人は115人と回答者の30.83%を占めている。また、京都に比較的近い中部や四国地方の人よりも、関東地方在住者の申し込み率が高いことがわかる。墓地の場所と契約者の居住地について他の樹木葬墓地で行われた調査結果を見てみると、やはり地元在住者か関東地方在住者の割合が高い傾向にある。今回の調査でも、確かに京都府を含む近畿地方の割合は高かったが、その次に関東地方の割合が高いことを考えると、樹木葬という墓所の選択には二極化の傾向が見られることがわかる。一つは居住地の近くに墓所が欲しいと望む、比較的利便性を重視する人々であり、もう一つは、遠くても良いので自分の好きな墓所に眠りたいという、墓所の選択に積極的な意味合いを持たせる人々である。後者の場合、現在のところ関東地方在住者の割合が高いと言える。
ちなみに、回答者が子供時代に過ごした場所を問う設問では、割合の大きい順に、京都府含む近畿地方が48.94%、関東地方が13.83%、中部地方が10.64%と、若干近畿地方以外の割合が増える結果となった(n=376)。
意識調査結果―――墓所に関する意識
回答者の属性を確認したところで、次に回答者の墓地や樹木葬に関する意識を見ていきたい。
問1では、契約した樹木葬墓地を知るきっかけとなった媒体(3つ以内複数回答)を訪ねた。上から多い順に「インターネット」234(60.62%)、「新聞・情報誌」93(24.09%)、「友人、知人からの紹介」36(9.33%)、「テレビ報道、ラジオ番組」29(7.51%)と続き(n=386)、圧倒的にインターネットを使用して情報を検索した人が多いことがわかる(図5)。インターネットの普及率がますます高まっている現在の状況において、墓の情報もその他の日常的な情報と同様に、手軽な手段であるインターネットから収集する場合が多いと考えられる。この流れは、新聞やテレビなどから受動的偶発的に情報を受け取るのではなく、自ら進んで情報を得ようとする傾向の現れとも読み取ることができるだろう。ただし、ヒアリング調査で見られたように、契約者本人ではなく、より若い世代の子供や孫が、本人の代わりにインターネットを使用して情報を収集している場合もある。
次に問2では、契約墓所以外にも他の墓所を検討したかどうかを尋ねた。「比較検討した」回答者は272人(69.92%)、「比較検討していない」回答者が111人(28.53%)、無回答が6人(1.54%)であった(n=389)。問2-1においては、問2で「比較検討した」と答えた人に、どのタイプの墓所と比較したのかを尋ねたところ(3つ以内複数回答)、多い順に「民間霊園の樹木葬」163(59.93%)、「寺院の墓」79(29.04%)、「納骨堂」43(15.81%)、「公営霊園の樹木葬」37(13.60%)と続いた(n=272)。「民間霊園の樹木葬」が多いのは、先に見たようにインターネットが情報検索の主要な手段であるため、情報として比較的多く目に入るからだろうか。しかし「寺院の墓」も次点で多いことを考えると、すでにある実家の墓に入る選択肢も、最初から排除されていたわけではなく、決定の過程で少なからず検討されていたと言うこともできるだろう。
問3では樹木葬の契約が誰のためであったのかを尋ねた(該当するもの全て複数回答)。「自分」という回答が最も多く309(79.64%)、次に「配偶者」256(65.98%)、続いて「自分の母」67(17.27%)、「子供」64(16.49%)、「自分の父」47(12.11%)と続いた(n=388、図6)。「自分」が最も多く、その次に「配偶者」の割合が大きいという結果は、夫婦での利用が多いことを示している。実際にカン綜合計画提供の資料によると、2017年7月18日時点での区画利用形態の割合は、一人用区画が22.75%、二人用区画が77.25%となっているため、夫婦での二人用区画の利用が主流となっていると言える。
次に問4では、樹木葬墓地を購入する前に、入ることのできる墓があったのかどうかを尋ねた。その結果、「継ぐ立場にある家の墓があった」76人(19.59%)、「継ぐ立場にはないが、入ろうと思えば入ることができる家の墓があった」が77人(19.85%)、「自分の代で買った墓があった」26人(6.70%)、「家の墓はあったが、入ることができる墓ではなかった」53人(13.66%)、「墓はなかった」143人(36.86%)、「その他」13人(3.35%)となった(n=388)。およそ半数程度の割合で、入ることができる墓があった人とそうでない人がいたことがわかる。
それでは、なぜ墓があるのにあえて新たに樹木葬墓地を購入したのか。問4で「継ぐ立場にある家の墓があった」、「継ぐ立場にはないが、入ろうと思えば入ることができる家の墓があった」、「自分の代で買った墓があった」と回答した人に、次の問4-1でその理由について訪ねたところ(3つ以内複数回答)、多い順に「子供に継承のことで負担をかけたくないから」104(58.10%)、「自然に還ることを希望しているから」80(44.69%)、「お墓が遠いところにあるから」72(40.22%)、「継承者がいない、あるいはいなくなる可能性があるから」71(39.66%)と続いた(n=179、図7)。
この結果をこれまでの調査と比較してみると、2002年の岩手県祥雲寺での調査では、同じ質問と選択肢に対し、多い順に「自然に還ることを希望している」81.0%、「子供に継承の負担をかけたくない」40.0%、「継承者がいない」23.0%、「代々守る家の墓に入りたくない」「人間関係が煩わしい」がそれぞれ15.0%となっていた4。顕著な違いとしては、「子供に負担をかけたくない」と「自然に還りたい」という選択肢が逆転しているということだろう。今回の回答者たちにおいては、自然との関わりという観点よりも、子供に負担をかけない墓所としての樹木葬の機能がより重視されていると言える。
次の問5では、今度は回答者全体に樹木葬を選択した理由を尋ねた(3つ以内複数回答)。それぞれの選択肢が拮抗しその間ではっきりとした差異は見られないものの、多い順に「自然に還ることができるから」230(59.90%)、「墓のことで周囲に迷惑をかけたくないから」228(59.38%)、「継承者がいなくてもいいから」224(58.33%)、「樹木葬の趣旨が気に入ったから」152(39.58%)となっている(n=384)。選択肢が少なく、回答が特定の選択肢に集中してしまった印象があるが、これまでの調査で優勢であった「自然に還ることができる」と言う選択肢が、「継承者がいなくてもいい」や「周囲に負担をかけたくない」という選択肢と同程度の割合になっていることが見て取れ、問4-1での考察を補強する結果となっている。
しかし、単に「自然に還ることができる」「継承者がいなくてもいい」「周囲に負担がかからない」という点だけで見れば、現在、ほとんどの樹木葬墓地はその条件を満たしていると言える。なぜ、数ある樹木葬墓地の中からこの樹木葬を選択したのか。問6ではその理由を尋ねた(5つ以内複数回答)。当初、筆者はこの墓地を契約する人たちの意識として、日本有数の観光地である「京都」のブランド性が関係していると予想していた。しかし、結果はこの予想を裏切っていた。まず、最も多く選ばれているのが「お寺が管理をしてくれるので安心だから」233(60.36%)、次いで「永代供養をしてもらえるから」226(58.55%)、そして「京都が好きだから」133(34.46%)、「お寺の境内の中で神聖な雰囲気を感じられるから」127(32.90%)、「お寺の景観や由緒が気に入ったから」125(32.38%)、「自分の住んでいる地域の近くにある、もしくはアクセスが良いから」119(30.83%)と続いた(n=386、図8)。抜きん出て高い数値になったのが「お寺による管理の安心感」と「永代供養」だが、これは樹木葬を選択するにあたり、墓所としての永続性が保証されているかどうかが最も重要な関心ごとになっていたことを示唆している。そして、その永続性を保証するものとして、「お寺」の存在が欠かせないとも考えられている。この点について示唆的なのが、ヒアリング調査で何名かの人が口にした「有名寺院なら廃寺の心配がない」という言葉である。これは墓所の維持という安心感を得るために、有名寺院というブランド性が一役買っていることを示している。お寺の存在は、宗教的な安心感もさることながら、それ以上に信頼性のある墓所の管理者としての期待がされているのだ。先に見た問4-1や問5も併せて考えるならば、回答者たちの意識としては、子孫に墓守の負担はかけたくないものの、自らの眠る墓所が将来的にきちんと管理され、荒れ果てずに存続することを強く望んでいるということになるだろう。
次の問7では同じ自然に還る葬法でも、なぜ「散骨」ではなく「樹木葬」を選択したのかを尋ねた(3つ以内複数回答)。最も多いのが「埋葬した場所が特定でき、参拝ができるから」287(74.93%)、「管理や手入れが行き届いているから」が213(55.61%)、「墓地として許可を得た場所なので安心できる」が200(52.22%)となった(n=383)。ここでもやはり、墓所としての場所が保証されていること、またその管理が重要であるという意識が窺える。
次に問8では埋骨された後の祭祀を行う人の有無を尋ねた。最も多いのが「決まった人がいる」195人(50.91%)、「決まってはいないが、期待する人がいる」63人(16.45%)、「期待はしないが、墓を訪れて祭祀してくれる人がいれば、それはそれで嬉しい」103人(26.89%)、「決まった人も希望する人もいない」「祭祀を希望しない」がそれぞれ11人(2.87%)となった(n=383、図9)。先の祥雲寺で行われたアンケートでは、同じ質問に対し、「決まった人がいる」16.9%、「期待する人がいる」13.7%、「期待はしないが、祭祀してくれる身内の人がいれば、それはそれで嬉しい」46.5%、「いない」と「希望しない」を合わせて16.9%、「わからない」6.0%となっているように6、死後の祭祀を期待しないか、あるいは非常に消極的な形で期待している。それに対し、京都の樹木葬墓地申込者の場合は、死後の祭祀が行われることを期待している人がほとんどであることがわかる。そして、問8-1で明らかなように、この場合の「決まった人」や「期待する人」とは、多くの場合が子供や家族などの身内である(図10)。
先に見た問4-1と問5では、継承の必要ない墓(樹木葬)を選択した理由として、子供に迷惑をかけたくないという意識が最も強いことを確認したが、この結果はこれと矛盾しているようでもある。墓守の負担はかけたくないが、墓参に訪れ祭祀してくれることは期待しているように読み取れるからである。しかし、ここには回答者の微妙な本音が見え隠れしていると考えられる。例えばヒアリング調査で、「アンケートには『決まった人がいる』と書いたけど、あれは別に強制ではないのよ。観光のついでか何かで来てくれれば嬉しいと思っただけで。」と語った女性がいた。問4-1、問5の結果から考えても、子供の義務として墓参りを希望する回答者はほとんどいないが、この女性が語るように、何かのついでに来てくれることを期待している回答者は多いように思える。これは、祥雲寺のような里山型の樹木葬墓地が市街地から離れた山奥であるのに対し、京都の樹木葬墓地が観光地の只中に所在するという要素が強く影響していると考えられる。墓所がアクセスの悪い遠方にあるとすれば、周囲への負担を考慮し祭祀の期待を遠慮するかもしれないが、逆に多くの人が訪れたいと思うような場所であれば、訪れてもらうこと自体が、墓参者を楽しませることにつながり、積極的に期待するという意識が働くと考えられる。これまでの樹木葬墓地はアクセスの悪い場所にあることが多かったため、墓参への期待度は低く、井上が指摘するように「自然の永遠性」に家族の繋がりを託しているような傾向があった。しかし今回のようにアクセスも良く、観光地という周囲の環境で墓参者を楽しませることができる樹木葬墓地であれば、墓参への期待度は高くなると推測できる。
次に、問9において樹木葬墓地への埋葬方法を尋ねたところ、「全骨納骨」が311人で81.84%、「分骨して納骨」が69人で18.16%となった(n=380)。意外にも低い割合のように思えるが、関西では火葬場での収骨量自体が少ないため、そもそも分骨するほどの量ではない可能性もある。問9-1において「分骨」を選択した人に残りの遺骨の行方を尋ねたところ(該当するものすべて複数回答)、「その他」が最も多く21(30.00%)、次いで「オブジェなどに加工して自宅に安置」14(20.00%)、「散骨」「骨壷に納めたまま自宅に安置」がそれぞれ13(18.57%)、「ペンダントなどに加工して身につける」が12(17.14%)、「既存の墓に納骨」が8(11.43%)であった(n=70)。「その他」の内訳としては、建仁寺の近くでもある本願寺大谷廟への納骨という回答が目立った。ちなみに、大阪には骨仏で有名な一心寺があるが、一心寺への納骨という回答はなかった。
問10では、遺骨、自然、魂についての考えが問われた。最も多く選ばれたのが「魂の存在はわからないが、故人の遺骨は分解されて土となり、自然の循環の中で生き続ける」284人(75.13%)、次いで「故人の魂は、樹木葬墓地における植物や昆虫など、自然物の中に宿る」43(11.38%)、「遺骨はただの物質だと思っているので、特にイメージすることはない」28人(7.41%)、「その他」23人(6.08%)となった(n=378)。魂の存在を前提としている選択肢を選んだ人は少数派であったが、魂の存在を不問にし遺骨と自然物の関係を記述した選択肢は、大多数の人が選択する結果となった。魂の存在は信じないが、ほとんどの人は遺骨を単なる物質とは見なしていないことがわかる。
次に問11だが、これは問6でも一定の得票率を得ていた墓所の雰囲気に関わる設問である。墓所を訪れる時にどのような気持ちになるかを尋ねたところ、多い順に「緑が多く、穏やかで落ち着いた気持ちになる」220人(57.89%)、「死者が眠っている場所なので、神聖で厳粛な気持ちになる」90人(23.68%)、「親しかった死者と、じっくり語り合えるような気持ちになる」61人(16.05%)、「特に何も感じない」2人(0.53%)、「その他」7人(1.84%)となった(n=380)。樹木葬の墓所は、死者の存在を意識するような場所と言うよりも、緑の多さや雰囲気の良さなど、生者のための場所という意識が強いと言えるかもしれない。しかし、場所に対する人の意識は重層的であるので、複数回答の場合はまた異なる結果が得られた可能性もある。
墓参、合同供養祭に関する意識について
ここからは墓地そのものではなく、墓参や合同供養祭などの、墓地に付随する実践や行動に焦点を当てた設問になる。
まず問12では、樹木葬墓地で毎年春と秋に二回行われている合同供養祭への参加状況を尋ねた。合同供養祭は、献花・焼香を含む墓前での法要、住職の法話、茶話会などが行われ、全体として1時間半程度のイベントとなっている。多い順に「体調、日程が許す限り参加するようにしている」226人(60.92%)、「あまり積極的に参加はしていない」128人(34.50%)、「参加したいと思わない」17人(4.58%)となり(n=371)、6割以上の人が積極的に参加している様子がわかった。それでは、なぜ合同供養祭に参加するのかを、問12で「参加する」を選択した回答者へ尋ねたところ(当てはまるもの全て複数回答)、多い順から「住職の法話が聞けるから」157(70.09%)、「故人を供養できるから」139(62.05%)、「この墓地が縁で知り合った人たちに会えるから」74(33.04%)、「京都に行けるし、京都観光もできるから」50(22.32%)、「その他」14(6.25%)となった(n=224、図11)。意外だったのが、このような共同の墓所で見られる共同体意識、すなわち「墓友」への志向がそれほど高くない点である。該当するものを全て選択可能な形式になっているにもかかわらず、全体の三分の一程度の割合にしか達していない。
1990年代前後に登場し始める個人を単位とする共同の墓については、これまでそこに集う人々の共同性に注目が集まってきた。合同慰霊祭を始め、クラブ活動や会報誌上での意見交換など、生前から様々な交流の機会を持つことで、同じ墓所に入る人同士の連帯を強める取り組みがなされていたのである。樹木葬墓地でもそのような共同体意識が見られるという報告もあった。しかし、これはもちろん、連帯意識を醸成する仕掛けを墓地の主催者側が積極的に行うかどうかで変わってくる。そのため、今回の樹木葬墓地で共同体意識が低いように見えるのは、会員同士の交流事業をそれほど積極的に行わない運営方針によるのかもしれない。実際に筆者が2017年10月の合同供養祭を見学した感想では、夫婦や家族連れで訪れている人も多く、横の繋がりよりも家族それぞれの中での繋がりが重視されているように見えた。なお、逆に「積極的に参加しない」と回答した人にその理由を尋ねたところ(当てはまるもの全て複数回答)、「予定が合わないから」60(40.82%)「遠方に住んでおり参加しづらいから」57(38.78%)、が主流な回答となった(n=147)。
次に、樹木葬墓地への墓参に関して、すでに故人を埋葬した人と、生前契約の人に分けて質問を設けた。問14では、すでに故人を埋葬した人を対象に、1墓参の頻度、2どのような機会に墓参するのか(当てはまるもの全て複数回答)、を尋ねた。1では、多い順から「年に2~3回程度」88人(55.70%)、「月に一回程度」40人(25.32%)、「年に一回程度」26人(16.46%)、「週に1回程度」1人(0.63%)、「それ以上」3人(1.90%)となった(n=158)。2では、多い順に「特定の機会に限らず、好きな時に訪れる」90(56.60%)、「故人の命日」84(52.83%)、「合同供養祭」81(50.94%)、「お彼岸やお盆」76(47.80%)、となった(n=159)。故人の命日や合同供養祭、お彼岸やお盆などの時間的な区切りではなく、「特的の機会に限らず好きなときに訪れる」が選ばれたのは意外な結果であった。死者自身の時間の流れというより、生者自身の時間の流れが重視されていると言えるかもしれない。
次に生前契約の人を対象にした設問で、1契約後墓地に来る機会はあるか、2あるのであればその理由は何か(当てはまるもの全て複数回答)を尋ねたところ、1では「はい」と答えた人が176人で81.86%、「いいえ」が39人、18.14%であり(n=215)、多くの人が、墓参対象者がいないにもかかわらず、契約後に墓地を訪れていることがわかった。1で「はい」を選択した人にその理由を尋ねたところ(あてはまるもの全て複数回答)、「寺の境内の雰囲気を味わうため」96(54.55%)、「自分の眠る場所を確認するため」91(51.70%)、「家族や友人に自分の墓所を見せるため」89(50.57%)、「その他」22(12.50%)となった(n=176)。
最後に問16では、墓地使用料、年会費、合同供養祭、全体の4項目に分けて五段階の満足度を尋ねた(図12)。1が最も満足度が低く、5が最も満足度が高い場合に選ぶ数字となる。なお、今回の調査では、該当の数字ではなく「満足」という文字に○をつけた回答者が多かったため、この場合には数字による評価とは別に集計を行った。この結果を見ると、全ての項目で最高評価の5を選ぶ人が最も多く、高い満足度が得られていることがわかる。
信仰や宗教的な行動に関わる意識調査
ここからは、直接樹木葬墓地に関わるものではないものの、樹木葬契約者の宗教的背景や実践を確認していく。
まず、家の宗教ではなく契約者個人の信仰する宗教についての設問では、「仏教系」112人(28.79%)、「神道系」6人(1.54%)、「神仏両方」22人(5.66%)、「キリスト教系」10人(2.57%)、「それ以外の宗教」1人(0.26%)、「信仰する宗教なし」187人(48.07%)、「その他」17人(4.37%)、無回答34人(8.74%)となった(n=389、図13)。これを全国的な調査と比較してみると、20年以上前のものであるが1995年に行われた朝日新聞社の世論調査の場合、「仏教系」26%、「神道系」2%、「神仏両方」1%、「キリスト教系」1%、「それ以外の宗教」2%、「信仰する宗教なし」63%、「その他・答えない」5%となっている。また、近年の調査で類似のものとして2008年に国際比較調査グループ(ISSP)によって行われた調査では、「仏教」34.0%、「神道」2.7%、「宗教を信仰していない」49.4%となっている10。このように比較してみると、年齢層が60歳代~70歳代に偏っているにも関わらず、今回の調査対象者は全国一般の人々の信仰状況とそれほど変わらないか、無宗教を自認する人が若干多いようである。
次に、問18では家庭における死者供養あるいは追憶の場所があるかどうかを尋ねた。その結果、「自宅に仏壇がある」140人(35.99%)、「自宅に仏壇はないが、写真や花を飾ったりして死者を追憶する場がある」130人(33.42%)、「手元供養をしている」18人(4.63%)、「何も持っていない」94人(24.16%)、無回答7人(1.80%)となった(n=389)。「仏壇」の有無は別にしても、全体の約7割が死者を偲ぶための場所を自宅に持っていることがわかる。これは回答者の平均年齢が約69歳であるため、両親や配偶者など、親しい近親者がすでに他界している人の割合が高いためと考えられる。
問19では、死者への追悼、あるいは供養をどのようなものと考えているかを、具体的に自由記述で回答してもらった。方法としては、回答の記述からいくつかの要素を抽出し、それぞれの要素を拾い上げる形で集計を行なった(図14)。アンケート票には回答例として「故人の写真へ語りかける、線香をあげる、心の中で感謝を捧げる、など」という文章があったため、若干それらの要素へ偏った印象もあるが、多かった回答順に「故人への感謝」121(38.54%)、「故人への語りかけ」115(36.62%)、「線香をあげる」89(28.34%)、「故人を思い出す、あるいは忘れない」78(24.84%)、「お供えものをする」44(14.01%)となった(n=314)。「故人への語りかけ」の回答者の中には、明確な対象として「故人の写真」を挙げた人が60人いる。また、「お供えもの」の内訳として、「花」を挙げた人が17人、「水やお茶、食べ物等」を挙げた人が27人いた。
この結果を見ると、およそ4割の人が、故人への供養とは感謝をすることであると考えていることがわかる。また、心の中、あるいは写真や仏壇などの対象物に向かって、故人を思い出したり、話しかけたりする人が3割程度いることもわかる。このことから、「供養」と言ったときに想定されるような宗教的儀礼は介在せず、もっぱら個人的な行為として死者への追悼や供養が行われている点が確認できる。また、墓との関連で意外に思えたのは、「墓参」を挙げる人が非常に少なかった点である。先に問8で見た「墓の祭祀の希望」との関連で捉えるならば、墓参に訪れて欲しいとは思っているが、墓を訪れること自体が供養になると考えているわけではないということだろう。
次の問20では、回答者が実際に行なっている宗教的実践の頻度について質問がなされた。その結果は以下の表とグラフの通りである(表1、図15)。なお、4については、「祭祀の主催者のみお答えください」としたため、回答者の母数は3分の2程度となっている。
1~3に関しては、それぞれ回答者の5割以上が日常的にこれらの実践を行なっている様子がわかる。4に関しては、年忌法要の主催者を対象にしたため、回答者は全体の7割程度になっているが、それでも全体の4割程度の人が、年忌法要を定期的に行っていることがわかる。問19との関連で考えれば、これらの行事や実践は故人を本当の意味で供養することになるとは考えられていないが、慣習としては根強く残っているということだろうか。
次の問21では、墓や死者祭祀に関連した行為についての意識を問う質問がなされた。その結果は以下の表とグラフの通りである(表2、図16)。
意外なことに、問4で樹木葬を選択した理由に多くの人が継承の問題を挙げていたにもかかわらず、1墓を継承することを「とても重要」「まあまあ重要」と回答した人が合わせて約40%もいた。さらに、問19で「故人を供養するとはどのようなことか」について、「墓参り」や年忌法要などの仏教的祭祀を挙げた人は少数だったにもかかわらず、4や5で「お盆の行事や墓参り」「年忌法要」を「とても重要」「まあまあ重要」と回答している人は全体の60%~70%にものぼった。
次に、これと関連して、問22では1先祖を敬うことをどのように感じるか、また2自分にとっての先祖とは誰を指すかが問われた。1では「とても重要」147(39.10%)、「まあまあ重要」164(43.62%)、「あまり重要でない」20(5.32%)、「重要性を感じない」15(3.99%)、「必要性を感じない」5(1.33%)、「わからない」25(6.65%)となった(n=376、図17)「とても重要」「まあまあ重要」を合わせておよそ82%もの人が先祖を敬うことを大切に考えていることがわかる。しかし、これはいわゆる「家の先祖」と呼べるような、系譜的な死者のことを指していると言うよりは、2を見ればわかる通り、多くの場合両親や祖父母などの身近な死者が想定されているのだと考えられる(図18)。ただし、「5.自分の実家の、祖父母よ
り上の世代」が「3.自分の実家の祖父母」に匹敵する程度に選択されていることから考えて、配偶者ではなく自分の家について言えば、ある程度系譜的な先祖が想定されているとも言えそうだ。この点については男女によって大きく差が出ると考えられる。
最後に、葬式に対する回答者の意識を訪ねた。アンケート票では「故人をすでに埋葬した人」と「生前契約の人」で場合分けをしたが、実際には故人をすでに樹木葬墓地に埋葬し、かつ自身も樹木葬墓地を生前契約している人もいるため、両方の場合に回答する人が多く見られた。また、このような場合、前者と後者で回答が異なっていることも多いため、今回はあえて両方に回答していても無効とせずカウントしている。
問23ではすでに行った、あるいはこれから行おうとする葬儀の形式を回答してもらった。結果、すでに故人を埋葬している場合は「仏式」131人(73.60%)、「神道式」4人(2.25%)、「キリスト教式」1人(0.56%)、「無宗教」35人(19.66%)、「その他」7人(3.93%)となり(n=178)、生前契約の場合は「仏式」146人(62.93%)、「神道式」0人(0%)、「キリスト教式」3人(1.29%)、「無宗教」58人(25.00%)、「その他」25人(10.78%)となった(n=232、図19)。両方の場合に回答している人は47人である。すでに故人を埋葬している場合も、生前契約の場合も圧倒的に「仏式」との回答が多数を占め、その次に多いのがどちらの場合も「無宗教」になっているが、これは生前契約の場合が5%程高い。また、生前契約の場合は「その他」も1割程度を占めているが、ここには「未定」「考え中」や、「葬儀はしない」と回答している人が多く見られた。
問24ではすでに行った、あるいはこれから行なおうとする葬儀の規模を訪ねたが、すでに故人を埋葬している場合と生前契約の場合で大きな違いが見られた。前者については、「一般的な葬儀」62人(35.23%)、「家族葬」97人(55.11%)、「一日葬」7人(3.98%)、「直葬」10人(5.68%)である(n=176)。後者については「一般的な葬儀」10人(4.55%)、「家族葬」151人(68.64%)、「一日葬」17人(7.73%)、「直葬」42人(19.09%)となった(n=220、図20)。両方の場合に回答している人は41人である。この結果を見ると、葬儀の小規模化が顕著に現れているうえ、葬儀自体を行うつもりのない人も一定数いることが明らかであるが、それは特に自分の葬儀を考える場合に明白になっていることがわかる。
最後の問25では、戒名を希望するかどうかを尋ねたが、「自分が亡くなったら戒名を希望している」48人2.53%)、「戒名は必要ないと考えている」241人(62.92%)、「自分はどちらでもいいと考えており、遺族に任せるつもりでいる」94人(24.54%)となり(n=383)寺院との関わりが深い墓地であるにもかかわらず、戒名を希望する人は少ないということが明らかになった。
2.追加アンケート
調查方法
2017年10月21日から23日にかけて行われた秋季合同供養祭において、参加者一グループにつきそれぞれの代表者一名に追加アンケート票を配布し、その場で記入してもらった。回収数は、両足院28票、正受院26票、即宗院47票、荘厳院5票、計106票となった。
回答者の属性
回答者の平均年齢は68.22歳(n=95)で、現在の居住地は「京都府在住」が40人(40.00%)、「京都以外の近畿地方(大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県)」が36人(36.00%)、「その他(茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、島根県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県)」24人(24.00%)であった(n=100)。
調查結果
No.1では、全体アンケートの問6での結果を受け、京都への関わりの深さがどの程度アンケート結果に影響しているのかを調べるため、1京都在住者の場合には在住年数を、2京都在住でない場合には京都を訪れる頻度を尋ねた。その結果、1京都在住者の回答者42人のうち、平均居住年数は38.48年で、最も多かったのが「31年以上」で26人となった(n=42、図21)。次に2京都在住でない回答者54人の場合、月の平均訪問回数は0.85回となり(n=54、図22)比較的多く京都を訪れる機会があることがわかった。どちらの場合にも、全体的には京都との関わりが強いことが見て取れる。
No.2では、元々のお寺との関係がどのようにアンケート結果に影響しているのかを調べるため、寺檀関係の有無を尋ねた。その結果、回答者103人中、「あった」が26人(25.24%)、「なかった」が77人(74.76%)となり(n=103)寺檀関係にある人の方が少数派であることがわかった。全体アンケートの間20、問21では、墓参や年忌法要などの仏教的行事を積極的に行なっている様子が見て取れたが、それは檀那寺との関係から行っているわけではなく、文化あるいは慣習として維持されているということだろうか。
次にNo.3では、全体アンケートにおける問6の結果を受け、樹木葬墓地を選択する際のそれぞれの要素の重要度を5段階で表現してもらった。その結果は以下の表とグラフのとおりである(表3、図23)。
僅差ではあるが、やはり「3-(6)墓地の管理をしなくても良いこと」や「3-(9)永代供養付きで、なくなったら自然退会等の契約内容」など、墓所の管理や祭祀の重要度がその他の項目と比較しても高いことがわかり、問6の結果と重なっている。しかし、ここで最も4と5が多い結果となっているのが「3-(3)墓所の景観や雰囲気が良いこと」であるのは注目すべきだろう。墓所の管理の仕方はもちろん選択にあたっては重要な要素となるが、その他の決定的な要素が、景観や雰囲気の良さなどの五感的なものであると言えるからである。ヒアリング調査の中でも、「なぜこの墓所を選択したのか」という問いに対し、「見学に来て、なんとなくここにしようと思った。」「雰囲気で決めた。」など、言語化できない直感の部分で墓所を選択したと語った人は少なくなかった。私たち第三者が考え、また期待しているほど、必ずしも墓所の選択に筋道だった理由があるわけではないと言えそうである。
今回の調査で一つ興味深い出来事があった。合同供養祭の当日に筆者が追加アンケート票を配っていると、一人の女性がアンケート用紙を記入しながら、「この間のアンケート(郵送で配布された全体アンケート)に主人と一緒に答えていたら、今まで曖昧だった自分の考えが、だんだん整理されてはっきりしたって主人が言っていたの。原本は返送したけど、あとで自分たちで見返せるようにコピーをとって保管してあるのよ。」と声をかけてきた。この女性やその夫にとって、墓の選択とは、実は理路整然とした思考の末に行われたものではなく、誰かに問われかけて初めてその意味を考え、答えを導き出すものだったのである。その意味で、私たちが行っている調査が、再帰的に墓地選択者たちの意識を形成する一つの源泉となっている点には、自覚的でいなければならないだろう。
最後に墓地の購入が可能となる価格帯を尋ねたところ、一人用価格の場合、「40万円まで」7人(12.28%)、「50万円まで」32人(56.14%)、「60万円まで」7人(12.28%)、「70万円まで」4人(7.02%)、「80万円まで」1人(1.75%)、「100万円まで」6人(10.53%)となった(n=57、図24)。二人用価格の場合は、「50万円まで」6人(8.82%)、「60万円まで」4人(5.88%)、「70万円まで」23人(33.82%)、「80万円まで」12人(17.65%)、「90万円まで」5人(7.35%)、「100万円まで」16人(23.53%)、「100万円以上」2人(2.94%)となった(n=68、図25)。おおよそ希望される価格帯として、一人用ならば50万円程度、二人用ならば70万円~100万円程度であることがわかる。参考までに、京都市営深草墓地の平成29年度募集時の使用価格は、墓石等の建立費用とは別に1平方メートルあたり100万円となっている。
3.全体的な考察
以上、全体アンケートと追加アンケートで得られた結果を紹介してきたが、墓地の変遷における樹木葬墓地の位置付けに関しては槇村教授が、また葬儀の変遷における樹木葬申込者の位置付けという観点からは山田准教授がそれぞれコメントを加えているため、ここでは筆者の関心、すなわち今回のような都市の内部における樹木葬墓地に対する人々の意識が、これまでの樹木葬墓地とどのように異なり、またどこに連続性が見出せるのかという点から、若干の考察を加えたい。
これまで樹木葬墓地で行われてきた調査と比較してみると、今回の回答者たちの属性は、それほど変わらないように見える。つまり、親や祖父母と言うよりは自らの墓所のために樹木葬を選び、また子供がいるにもかかわらず墓の継承に関する「負担をかけたくない」との思いが強い人々であるという点である。
しかし、今回の結果を見ればわかるように、彼らの墓所への意識はそれまでの調査結果とかなり異なっている。異なる点をまとめるならば、以下のようになるだろう。1墓所を信頼性のある管理者に託すことで、その永続性を望むこと。2子孫による墓参に大きな希望を持っていること。3申込者同士の共同性が希薄であること。これには街中にあるという墓地の都市性と、歴史や伝統があり、観光地でもあるという今回の寺院の特性の双方が影響を与えていると考えられる。
まず1について考えてみると、カロートを持つ通常の墓と比較したときの樹木葬墓地の大きな特徴として、「遺骨が土に還る」というものがあった。この特徴は、継承の必要性を不問にするとともに、土に還った遺骨が周囲の植物などに吸収されることで自然の永遠性に回帰するという、ロマンティックな自然のイメージをももたらすものでもあった。しかし、今回の回答者たちが強く望んでいたのは、自然への回帰と言うよりは、寺院による墓所の永続的な管理や祭祀であった。従来の樹木葬申込者たちが自然の永遠性に死後の繋がりを託していたのとは対照的に、大本山の塔頭寺院が持つ伝統やブランドを信頼して死後を託していたのである。もちろん、それぞれの樹木葬墓地の持つ目的やそのために墓地に付与される役割は異なるため、これはある意味で当然の違いとは言える。しかし興味深いのは、遺骨を自然に還す形態をとっていても、墓所の見た目の美しさや小綺麗さは申込者にとっては重要なポイントであったという点である。自然の永遠性に回帰するならば、墓所の景観が自然の営みとともに変化するのは織り込み済みの事実である。今回の調査地の場合は、そうではなく、墓地がきちんと管理されることによって、自らの眠る墓所の景観が変わらないでいることが求められていると言える。
このように、墓所の管理や祭祀を寺院に委ねているように見えて、2を考えてみると、問8と問8-1で確認できたように、実際は子孫による墓参や祭祀は積極的に希望されている。問4-1や問5で樹木葬を選択した動機に「子供に迷惑をかけたくない」という意見が多かったにもかかわらず、この点は矛盾しているようにも思える。これについては、本文ですでに述べたように、墓地へのアクセスの良さとともに、墓所周辺が観光地であるという事実が影響していると考えられる。例えば地方の山の中や郊外の墓地の場合、その場所を訪れることに、墓参以外の目的はなかった。墓参のためだけにその場所へ行く必要があったのである。しかし、周囲が観光地であれば、墓参以外にも観光や食事、買い物など、様々な目的を持ってその場所を訪れることができる。墓参の方がその他の目的に従じることが可能となるのである。「子供に迷惑をかけたくない」と感じる申込者にとって、他の用事の「ついで」に来ることができる墓所では、より気軽に墓参を希望することができるのだろう。その意味では、里山や郊外の樹木葬を申し込んだ人々でも、負担にならない程度の場所に墓所があったならば、自然の永遠性に委ねるのではなく、自分の子供たちに墓参を望んだ可能性もある。
1,2からわかるように、墓所の管理や祭祀を寺院が責任を持って行ってくれるという点、また家族が墓参に来やすいという点は、3申込者同士の共同性の強弱にも関わっていると考えられる。槇村や中筋が指摘した、近年の共同墓所に見られる共同性は、いくつかの樹木葬墓地にも見られることが報告されてきた。例えば岩手県祥雲寺(知勝院)の樹木葬墓地でフィールドワークを行った人類学者のセバスチャン・P・ボレーは、自然再生活動や登山、合同慰霊祭などの行事を通じて、それまで面識のなかった樹木葬会員が共同性を作り上げていく様子を観察している。また、井上治代は自身が代表を務めるNPO法人エンディングセンターが運営する「桜葬」墓地において、自主的なクラブ活動や合同慰霊祭である「桜葬メモリアル」などの様々な「仕掛け」を通じて、会員同士によって生前の友達作りが行われていることを報告している。また、筆者自身も、共同性の強弱に濃淡はありつつも、樹木葬申込者たちは「自然に還る」という言葉を媒介に、他の申込者との価値観の一致という点にある種の安心を見出している様子を論じたことがある。しかし、今回の調査地のように、墓地の管理者に絶対的な信頼性があり、またその立地から気軽に家族の墓参を希望できるような墓所では、墓を媒介にした共同性は比較的希薄になるのだと考えられる。
以上、従来の樹木葬墓地との違いを三点にまとめて考察したが、今回の調査地の特徴であった街中や観光地という立地は家族による墓参を容易にし、また将来にわたっての永続性が見込まれる寺院が墓所を管理してくれるという点から、これまでのように「自然」や「墓を媒介にした共同性」に死後の繋がりを託さない樹木葬のあり方が明らかになった。しかし、従来の調査と対照的なこれらの結果から逆説的に浮き彫りになるのは、どのような墓地においても、周囲に迷惑をかけたくないと願う一方で、自らの眠る墓所を「無縁」のままにしたくないという墓地選択者たちの共通する思いである。家族による墓参が望まれないような場所では自然の永遠性や墓を媒介にした共同体に、墓参が容易な場所であれば家族にと、どちらも死後の墓所において何か自分以外の存在との繋がりを残そうとしているように見える。これは、共同体の一員から個人としての意識が強まり、墓すらも個人の選択になりつつある現代社会において、個人性を担保しつつ何らかの存在との関係で自己の死を捉えようとする、現代日本人の複雑な胸中を反映しているのかもしれない。
12 Sébastien Penmellen Boret, 2014, Japanese Tree Burial, Routledge, p. 166-167.
13 井上治代 2012 「集合墓を核とした結縁」 大谷栄一・藤本頼生編著『地域社会をつくる宗教』明石 書店、 p.239-263。
14 内田安紀 2017「現代日本における葬送と自然」 『宗教と社会』第 23 号、p.15-29。
カテゴリー一覧
タグ一覧