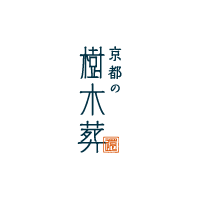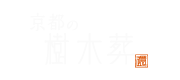実は全てのお骨を埋葬できる樹木葬は少ない
2025/08/09
お墓とは、本来「遺骨を埋葬し、供養する場所」です。
しかし近年の樹木葬の中には、限られたスペースを有効活用するため、「故人の遺骨を全ては埋葬できない」形式が増えています。
なぜ全骨を埋葬できないのか
1人や1家族に割り当てられるスペースが非常に小さいためです。
そのため、多くの場合は
- 粉骨(お骨を細かく砕く)を必須とする
- 専用の小さな骨壺に移し替えることを条件とする
といった運用になっています。
運営側(お寺や業者)から見ると、小さい区画に多くの利用者を募れるため効率が良く、短期間で回転率を上げられるというメリットがあります。結果、埋葬期間が3〜13年程度と短めの設定になっているところも少なくありません。
残りのお骨はどうなる?
埋葬しきれなかったお骨は、多くの場合、同じ敷地内にある永代供養墓(合祀墓)に納められます。
しかし、この永代供養墓は本来「永代期間終了後」に合祀するケースが一般的です。そこに一部を先に納めるというのは、「分骨や粉骨に抵抗がある方」にとっては納得しにくいケースかもしれません。
全骨埋葬できる樹木葬を選ぶポイント
私たちも他社の樹木葬を見学することがありますが、「全骨は納められない」という事実は、事前の情報だけでは分からないことが多いです。ホームページやパンフレットには、骨壺の大きさや埋葬方法の詳細が記載されていない場合も少なくありません。実際に現地を訪れ、ご住職やスタッフに直接お話を伺って、初めて分かるケースが多いのです。
では、どうすれば全骨を埋葬できる樹木葬を見極められるのでしょうか。
1. 写真から大きさをイメージする

関西で一般的な骨壺は5寸(直径約15.5cm、高さ約17.5cm)、関東では7寸(直径約21.7cm、高さ約25.5cm)です。樹木葬地の写真を見て、そのサイズの骨量が収まりそうか想像してみましょう。
例えば、直径20cmほどの区画で「4人分埋葬可能」と記載がある場合は、粉骨で少量ずつ納める方式か、深さをしっかり確保している方式のどちらかと考えられます。
2. 直接確認する
電話・資料請求・見学のいずれでも構いませんが、埋葬方法や骨壺のサイズについて直接質問するのが確実です。樹木葬選びでは、区画の景観や価格だけでなく、「どのくらいの骨量を納められるのか」を早い段階で確認しておくことが大切です。
お墓は長く使い続ける大切な場所です。だからこそ、事前にしっかりと情報を集め、納得したうえで選ぶことが何より重要です。
見学の際には景観や雰囲気だけでなく、埋葬の仕組みや条件も、ぜひあわせて確認してみてください。
ここからは、私たちカン綜合計画のご案内です

私たちは、もともと街づくり事業からスタートした会社です。
そこで培った景観設計や空間デザインの経験を活かし、お寺の境内にある樹木葬地の設計・販促・管理をお手伝いしています。
石材店ではないため、必要以上の石材は使わず、自然に還ることを大切にした設計を心がけています。緑に囲まれた、本来の意味での「樹木葬」をご案内しているのが私たちの特徴です。

また、私たちは樹木葬の販売を「商売」とは考えていません。あくまで人とお寺のご縁をつなぐお手伝いとして活動しており、今のところいわゆる営業活動は行っておりません。これまでのご縁はすべて口コミから生まれたものです。
だからこそ、費用や景観写真・動画、埋葬方法、永代期間、維持費など、気になる情報はすべてホームページで公開しています。
安心してご検討いただけるよう、私たちは情報開示を何よりも大切にしています。
カン綜合計画「京都の樹木葬ホームページ」👉https://jumokusou.jp/
全骨埋葬できる、個別区画、粉骨不要の樹木葬

東福寺 塔頭 正覚庵

建仁寺 塔頭 両足院

大徳寺 塔頭 正受院
私たちはご相談をきっかけに強引な勧誘やしつこい営業電話などは一切いたしません。
安心してご連絡ください。
カテゴリー一覧
タグ一覧