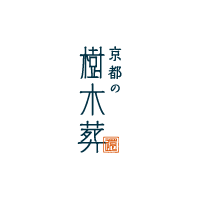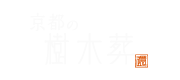分骨という選択――故人と心を結ぶために
2025/04/26
「分骨」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。 一人の故人のお骨を複数の場所に分けて安置するこの方法は、近年、供養の多様化とともに注目されています。 本記事では、分骨とは何か、その手続きや注意点、さらには仏教における分骨の歴史についてもご紹介いたします。
分骨とは
分骨とは、一人の故人のお骨を複数に分け、それぞれ別々の場所に安置することを指します。近年では、お墓が遠方にあってお参りが難しい場合や、家族が離れて暮らしている場合などに、手元供養や複数の墓所への埋葬を希望される方が増え、分骨が身近な選択肢となっています。また、樹木葬や散骨とあわせて、従来のお墓にも一部を納めるなど、多様な供養のかたちが広がっています。
分骨の注意点や必要な手続き

正式に分骨を行うには、いくつかの手続きが必要です。まず、火葬場で火葬の際に分骨を希望する場合は、「分骨証明書」の発行を申請します。この証明書は、後日墓地に納骨する際にも必要となるため、大切に保管しておくことが重要です。
すでに火葬後の遺骨を分ける場合でも、現在納められている墓地や納骨堂から改めて「分骨証明書」や「改葬許可証」が必要となる場合があります。分骨を希望する際は、事前に役所や墓地の管理者に手続き方法を確認することをおすすめします。
また、宗派や地域によっては分骨に対して否定的な考えを持つ場合もあるため、ご家族や菩提寺ともよく相談のうえ、理解を得たうえで進めることが大切です。
分骨の具体的なシチュエーション例
分骨は、さまざまなご事情や想いに応じて選ばれています。たとえば、一度行えば二度とお骨が手元に戻らない散骨や、埋葬後に基本的に取り出しができない樹木葬を選択される場合、お骨の一部を分骨して手元供養用の小さな骨壺に納め、身近に故人を感じられるようにされる方もいらっしゃいます。

また、一部は故人の出身地にある先祖代々のお墓へ納め、もう一部は現在の住まいから通いやすい近隣の霊園に分骨してお参りしやすくする、というケースもあります。このように、分骨は故人とのつながりを大切にしながら、生活環境や家族の想いに寄り添う柔軟な供養方法として活用されています。

お釈迦様の分骨について
分骨に対して「遺骨を分けることに抵抗がある」と感じられる方もいらっしゃいますが、実は仏教の祖であるお釈迦様も、入滅後に分骨されています。
お釈迦様が入滅された後、そのご遺骨は当時のインド各地の8つの部族に分け与えられました。それぞれの部族は仏舎利(ぶっしゃり)として遺骨を祀り、仏塔(ストゥーパ)を建立しました。さらに後の時代には、その仏舎利がさらに分配され、アジア各地へ広がりました。
この分骨の背景には、「お釈迦様の功徳をより多くの人々に届けたい」「広くご縁を結びたい」という願いが込められています。つまり、分骨は単に遺骨を分ける行為ではなく、故人の想いを広くつなげる尊い行いとして仏教でも受け継がれてきたのです。
分骨は、時に悩ましい選択にもなり得ますが、故人やご家族の想いを大切にするための柔軟な方法でもあります。大切な方との絆を守るために、心に寄り添った選択をしていただければと思います。
私たちはご相談をきっかけに強引な勧誘やしつこい営業電話などは一切いたしません。
安心してご連絡ください。
カテゴリー一覧
タグ一覧