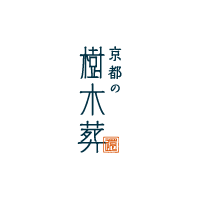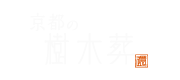樹木葬と永代供養墓の誤解されやすいイメージ——無縁仏を納めるお墓とは?
2019/08/30
京都の樹木葬は、永代供養(えいたいくよう)の形をとっています。樹木葬はお墓であり、そのため永代供養墓(えいたいくようばか・えいたいくようぼ)に分類されます。
しかし、「永代供養墓」と聞くと、合祀(ごうし)されるお墓を想像したり、身寄りのない方や無縁仏が納められるお墓と捉えたりする方もいらっしゃいます。
そこで今回は、近年注目を集める「永代供養墓」について詳しくご紹介します。
永代供養墓は無縁墓ではありません
永代供養墓とは、将来的にお墓参りが難しくなった場合に、お寺や管理者が代わりに供養を続けてくれるお墓のことです。これは、一つの仕組みとして成り立っています。
近年、少子化や核家族化が進む中で、お墓を継承することが困難になりつつあります。そのため、墓守の必要がないこの「永代供養」の仕組みが注目されるようになりました。
また、永代供養墓の多くは「合祀墓(ごうしぼ)」「合同墓」「合葬墓(がっそうぼ)」と呼ばれ、他の方のご遺骨と一緒に埋葬されるタイプのお墓が一般的です。
そのため、
「永代供養墓 = お墓を継ぐ人がいないためのお墓 = 無縁の方が入るお墓」
と誤解され、「無縁墓」と混同されることがあります。
永代供養墓の種類
永代供養墓は、大きく4つのタイプに分類できます。
- 永代供養合祀墓タイプ
最初から石塔や石仏などの供養塔に合祀されるお墓。 - 永代供養個人墓タイプ
さらに2つに分類され、- 永久に個別のお墓として管理されるもの
- 一定期間は個別墓として管理され、期間終了後に合祀されるもの
- 永代供養納骨堂タイプ
一定期間は納骨堂に安置され、その後合祀されるお墓。 - 永代供養樹木葬タイプ
京都の樹木葬はこのタイプにあたります。- 一定期間、樹木葬の区画に埋葬され、期間後に合祀されるもの
- 期間に関係なく、ずっと樹木葬の区画に埋葬されるもの
永代供養墓と一般的なお墓の違い
一般的なお墓は、石を墓標とし、家族が代々受け継ぐことを前提としたものです。多くの場合、墓守を務める人がいて、お寺の檀家になることが一般的です。
一方で、永代供養墓は墓守や継承者がいなくても供養が続けられる点が特徴です。さらに、お寺の檀家になる必要がないことも多く、遺族に代わって供養をしてもらえる安心感があります。
また、永代供養墓は一霊ごとに使用料が設定されているため、個人で利用する場合は従来のお墓に比べて費用負担が少なく済むこともメリットの一つです。
京都の樹木葬は永代供養墓の一形態
京都の樹木葬は、前述のとおり永代供養墓に分類されます。従来のお墓と異なる点は、供養の対象が石の墓標ではなく、生きた樹木であることです。
また、京都の樹木葬はお寺によって管理されているため、個別の区画が設けられているとはいえ、墓苑全体が「みんなのお墓」という意識のもと運営されています。そのため、同じ墓苑を利用する方々とのご縁が生まれ、自然と「墓友の輪」が形成されることもあります。
このように、京都の樹木葬は「無縁」になることはなく、むしろ「有縁」のお墓といえるでしょう。
弊社がご案内する 京都大本山 塔頭寺院の樹木葬

東福寺 塔頭 正覚庵

建仁寺 塔頭 両足院

大徳寺 塔頭 正受院
私たちはご相談をきっかけに強引な勧誘やしつこい営業電話などは一切いたしません。
安心してご連絡ください。
カテゴリー一覧
タグ一覧